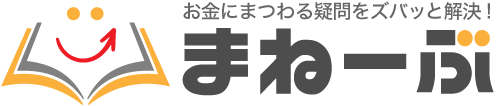必要保障額の目安はいくら?終身型と定期型をうまく組み合わせよう

生命保険に加入する際に死亡保障をいくらに設定するかは大切なポイントです。
万が一のときに遺族が過不足なく必要な保障額を受取るためには生命保険(死亡保障)に加入する段階でしっかりと計算しておくことが重要です。
しかし、保険料をムダにしたくないからとすべて終身保険で備えるのには無理があります。
定期保険も含めて、生命保険で必要保障額を用意するようにしましょう。
生命保険における必要保障額
生命保険(死亡保障)における必要保障額は、残された遺族が生活するために必要なお金のことです。
【支出】と【収入】から考える必要保障額
万一のことがあった場合に、必要な支出と収入を細かく挙げて計算方法するです。
この計算方法では遺族年金や相続財産など専門的な知識が必要となってくるため、専門家に相談するのもおすすめです。
(1)必要な支出を考える
- 死亡整理金
- 遺族の生活費、住居費
- 子どもの教育資金
葬儀関連費用で200万円程度の準備があればよいでしょう。
食費、交通・通信費、住居費など生活にかかる費用。
子どもがいて大学進学を考える場合は末子が22歳になるまでの教育資金を計算しましょう。
(2)収入にあたる保障を考える
- 貯蓄など相続財産
- 妻(遺族)の収入
- 死亡退職金
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 中高年寡婦加算
必要な支出に比べて、収入は会社員か自営業か、などそれぞれの環境により受け取れるものが変わります。
自営業であれば死亡退職金や遺族厚生年金は支給されないため、会社員よりも手厚い死亡保障を考える必要があります。
(1)―(2)=必要保障額
上記で挙げた【(1)必要な支出】―【(2)収入にあたる保障】=【必要保障額】となります。
この必要保障額の部分を生命保険(死亡保障)で用意することになります。
【現在の生活費】から考える必要保障額
こちらは簡易的な計算方法で、現在の生活費から遺族の生活費を算出します。
現在の生活費:月30万円
住居費:家賃月10万円
上記の家族構成で夫に万一のことがあった場合について考えてみます。
(1)末子独立までの遺族の生活費
末子が独立するまでの期間に必要な生活費は、現在の生活費の約70%を目安とします。
末子が22歳で独立するとして計算します。
【末子独立までの遺族の生活費】
現在の年間生活費×70%×(末子独立年齢―末子現在の年齢)
この式にあてはめると、
360万円×70%×(22歳-2歳)=5,040万円
となります。
(2)末子独立後の配偶者の生活費
子どもが独立した後、配偶者である妻が平均余命まで生活すると仮定して計算します。
この期間必要な生活費は現在の生活費の約50%を目安とします。
【末子独立後の配偶者の生活費】
現在の年間生活費×50%×末子独立の配偶者の平均余命
この式にあてはめると、
360万円×50%×38.13(50歳女性の平均余命)=6,863.4万円
参考:生命保険文化センター「日本人の平均寿命はどれくらい?」
(1)+(2)=【遺族に必要な生活費】1億1,903万円
夫(30歳)、妻(30歳)、子ども(2歳)の家族で月の生活費が30万円であった場合、遺族に必要な生活費は1億1,903万円となりました。
次に、夫に万一のことがあった場合に必要な生活費から得られる収入を引いていき、必要保障額を算出します。
妻が一生働かずに生活した場合、必要保障額は1億1,903万円ですが、仮に妻がパート・アルバイトなどで月13万円の収入を30年間得たとすると、そこから4,680万円引くことができます。
それだけでも、必要保障額は7,223万円まで減ります。
さらに、会社員である夫の死亡退職金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、中高年寡婦加算ももらえる可能性がありますので、ここからまた必要保障額は小さくなります。
1億円ともなると生命保険のみで準備するのは大変そうですが、収入も考えると現実的な金額になってきますね。
[macth url=”https://www.money-book.jp/7966″]
遺された人にどんな収入があるかを確認することが大切
次に考えるべきは、遺族が得られる収入です。
家族が働いていて収入がある場合はもちろんですが、それだけではありません。
日本は公的保険が充実しているため、万が一のことがあった場合に遺族が年金を受け取ることができる制度があります。
この分は、生命保険に加入して備える必要はありません。
世帯主などが死亡してしまった場合、遺族が遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取ることができます(※)。
※遺族共済年金は、現在では遺族厚生年金と一元化されています。
亡くなった人が自営業者か会社員かで、受け取れる年金の範囲が変わってきます。
自営業者の場合は遺族基礎年金のみですが、会社員は遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給できます。
ただ、受給するには条件があり、必ず受け取ることができるわけではありません。
遺族基礎年金は、「子または子のある配偶者」であれば受け取ることができます。
ただし、亡くなった人が子供の主たる生計維持者であり、子供が18歳になった年度の末日まで(子供が一定の障害等級に該当する場合は20歳になるまで)しか受け取ることができません。
遺族の子育てをサポートするための年金制度ということができるでしょう。
遺族厚生年金は、より優先順位が高い受給者がいなければ、「父母、孫、祖父母」でも対象となる場合があります。
亡くなった人が生きていた場合に受け取ることができる年金額の3/4が支給されます。
必要保障額のうち、働いて得られる給与と年金は、あなた自身が生命保険で備えておかなくても大丈夫な部分です。
必要保障額から遺族が得られる収入を差し引いた分を生命保険金で補えるように考えましょう。
ライフスタイル別、必要保障額計算ポイント

万が一のことがあった場合、貯蓄や生命保険でどれだけのお金を残すことができればいいのかは難しい問題です。
ネットで情報収集しても、「あなたにぴったりの保障額は○○万円です」と答えが見つかるわけでもありません。
自分で必要保障額を考えなければならないのです。
どうやって求めればいいかというと、まずは、遺族が使う生活費などの「支出」から考えることです。
いくつかのパターンに分けて、どのような費用が必要なのかを考えてみましょう。
①独身者の場合
独身だと、配偶者も子供もいないため、生命保険での保障は必要ないと思われがちです。
しかし、親に仕送りをしていたり、介護が必要だったりする場合は別です。
この場合は、あなた自身が親の生活費の一部を負担しています。
万が一のことがあった場合には、生前あなたが負担していた分に相当するお金を用意しておいた方がよいでしょう。
②夫婦のみの場合
夫婦のみの場合は、配偶者の生活費を用意できるようにしておく必要があります。
ただ、子供がいないのであれば、配偶者が職を見つけるまでの生活費と、充分な収入を得られない分を補うだけのものがあればよいでしょう。
具体的には、配偶者の収入によって必要保障額が変わりますが、それについては後述します。
また、住宅ローンの有無と、団体信用生命保険への加入状況によっても、必要保障額が変わってきます。
③子供がいる場合
子供がいる場合は、②の夫婦のみの場合よりも複雑になります。
家族が多い分だけ、生活費もたくさん必要になります。
しかも、子供が幼いのであれば、配偶者が仕事に出ることができなかったり、パート程度の仕事しかできなかったりするでしょう。
そういった状況も踏まえて、必要保障額を考えましょう。
このように、家族構成のパターン別に必要保障額が変わってくるのですが、計算するときのポイントがあります。
それは、「年間生活費」で考えるようにすることです。
例えば、「子供が小学校に通っているうちは、1年で○〇万円」、「配偶者が仕事を探さなければならない期間として、1年は○○万円」というようにです。
万が一のことがあってからの必要保障額全額を一度に計算しようとするから難しいのです。
短い期間に分割して、どれだけの費用が必要になるのかを考えていきましょう。
終身保険だけでは限界が。大きな保障に備えるには定期保険が便利!

万が一のことがあってからの費用から収入を差し引いても、必要保障額はかなりの金額になってしまいます。
特に、小さい子供がいる人の場合は多額になってしまいます。
食費などの生活費に加え、教育費がかさんでしまうからです。
子供1人あたりの教育費は、大学まで国公立でも1,000万円、私立学校や医学部など学費が高くなる場合では2,000万円にもなると言われます。
そのため、小さい子供がいる場合の必要保障額は3,000万円以上になる場合もあり得ます。
しかし、掛け捨ての保険は嫌だと終身保険で準備しようとすると月々の保険料が大きな負担となります。
定期保険と終身保険の保険料比較
終身保険「RISE」の保険料
30歳男性で終身保険の保険料がどれくらいになるか、シミュレーションしてみました。オリックス生命の終身保険「RISE」で、60歳払済の場合です。
| 終身保険「RISE」 | ||
| 保険金額 | 300万円 | 3,000万円 |
| 月額保険料 | 6,699円 | 65,220円 |
比較的よく加入される保険金300万円であれば、重い負担にならない保険料です。
しかし、3,000万円を終身保険で準備するのはまず無理でしょう。
しかも、3,000万円の必要保障額は、生活費や教育費などです。
つまり、年数が経てばたつほど必要保障額は減っていくのです。
そのために、一生涯の保障を用意しておく必要はありません。
定期保険「ファインセーブ」の保険料
子供が大学を卒業するまでの保障があればよいと考えられるため、一定期間だけ保障が受けられる掛け捨ての定期保険を活用してみましょう。
子供が幼いころになくなってしまう可能性を想定して、30歳男性の場合で、オリックス生命の「ファインセーブ」でシミュレーションしました。
なお、保険金額は3,000万円としています。
また、教育費用などの資金が必要になるのは「末子独立」のときまでなので、保険期間が30年の場合も試算しています。
| 定期保険「ファインセーブ」 | ||
| 保険金額 | 3,000万円 | |
| 保険期間 | 20年 | 30年 |
| 月額保険料 | 6,150円 | 7,830円 |
| 終身保険との合計 | 12,849円 | 14,529円 |
※終身保険は、上述の「RISE」で300万円の保険金で契約すると仮定
これなら、終身保険とあわせても、家計が回らなくなるような保険料にはならないでしょう。
このように、将来的に必要保障額が減っていくタイプの費用に備える場合は、定期保険を活用するのが賢い選択なのです。
まとめ
- 必要保障額は、それぞれのライフスタイルによって変わる
- 必要保障額を求めるには、万が一のことがあってからの費用から年金などの収入を差し引いても止める
- 多額だが、将来的に減っていく費用に備えるためには、定期保険の利用が有効